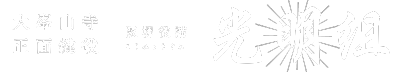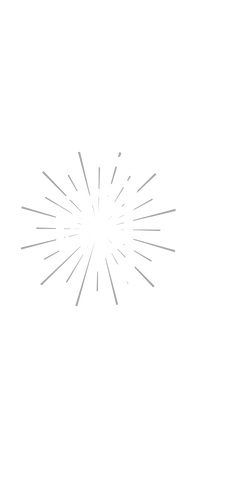
- 令和6年大峯山寺阪堺役講年番引継式
 令和6年(2024年)3月20日に大峯山寺阪堺役講年番引継式(おおみねさんじはんかいやっこうねんばんひきつぎしき)が行われました。
令和6年(2024年)3月20日に大峯山寺阪堺役講年番引継式(おおみねさんじはんかいやっこうねんばんひきつぎしき)が行われました。 - 令和6年髪切山慈光寺戸開式
 令和6年(2024年)3月16日土曜日に生駒山の髪切山慈光寺(こきりさんじこうじ)にて戸開式(とあけしき)が行われました。
令和6年(2024年)3月16日土曜日に生駒山の髪切山慈光寺(こきりさんじこうじ)にて戸開式(とあけしき)が行われました。 - 令和6年慈光寺護摩壇の準備
 令和6年慈光寺戸開式で行われる柴燈護摩供の準備を行いました。
令和6年慈光寺戸開式で行われる柴燈護摩供の準備を行いました。
阪堺役講 光明組とは
修験道修行の聖地である奈良県大峯山。
山上ヶ岳山頂の大峯山寺は7世紀末に修験道の祖である役小角(役行者)が、金峯山で感得した蔵王権現を刻んで本尊とし、蔵王堂を建てたことに始まると言われています。
その大峯山寺で伝統的に行われている毎年5月の戸開式、9月の戸閉式において、本堂の鍵の開け締めを行うなど、護持院ならびに吉野・洞川両区とともに重要な役割を担っているのが「阪堺役講」です。
私達光明組は阪堺役講に属する山上講として歴史ある修験道の文化を守るべく活動を行っています。

修験道について
修験道は古来より日本人が持っていたとされる山岳信仰、のちに伝来した仏教などと習合しながら飛鳥時代に役小角(役行者)が創始したとされています。
役小角については続日本紀や日本霊異記に記録が残っており、実在したと考えられていますが、鬼を従え点を飛ぶこともできたなど現実離れしていると感じるような伝説もあり、その生涯は謎に包まれています。
しかし、役小角が山岳修行により験を得ようとした背景には、当時大化の改新により混乱していた世の中を良くし、父母祖先の尊厳を守りたいというモチベーションがあったのではないかとする見方もあります。

山岳修行について
日本人は山に対して「神が宿る」と考えたり、「死者の魂は山上から彼岸に還る」と考えるように、私達が生きる日常の世界とは違う「この世とあの世のあいだにある境界」のような特別な場として畏敬の念を持って関わってきました。
山岳修行とは、このような別世界でいあば「擬死体験」をすることであるとも言われます。
非日常の体験によって「この世」に生きるありがたさや、先人たちから奇跡的なご縁によって繋がれてきた歴史によって存在する自分自身を見つめ直し鍛錬する機会が山岳修行であると考えています。
山の大自然に触れると、一歩踏み誤れば命を落とすような恐怖を感じたり、天候など自分の力ではコントロールできないことの存在に気づき、自分の無力さを感じながらも自分も大自然の一部なのだと母に抱かれたような安心感を得たりします。

大峯山には女人禁制や戸開式、戸閉式の作法など歴史的に大切に守られてきたルールも多く存在しています。
一見すると、そこに何の意味があるのか、時代錯誤だと感じるかもしれませんが、ここで修行を続けてきた先人たちに思いを馳せ、時間を超えて紡がれたご縁に感謝し未来につなげるためにこのような伝統的な文化を伝えていくことが大切なのではないかと考えています。
その意味では「山」は時間や空間を超えた存在としてあり、そこには「古い」も「新しい」も、「良い」も「悪い」もないのではないかと思えます。

修験道とは数ある宗教の一宗派としてだけではなく、修験「道」として実践を通してそれぞれの立場から気づきを得て現実から目をそらさず日常を生き抜くためのあり方そのものであると考えています。
修験道を日本の大切な文化として未来に継承するためにこのサイトを通して多くの人々にその魅力を知っていただき、できれば体感していただきたいと考えています。